味ひろ(新富町)
- 小松めぐみ
- 2019年4月8日
- 読了時間: 4分
更新日:2019年4月29日
東京都中央区湊3-13-15 ☎03-6280-5503
営業時間:18:00~21:30(最終入店)
定休日:不定休 コース予算:¥27,000〜(税別)要予約

師から受け継ぐ「味」の一字と
日本料理の本流を伝える心意気
新富町の静かな路地に建つ「味ひろ」は、郡司智裕氏(43)が2016年7月に開業した日本料理店。メディアの取材を受けるのは今回が初めてのため、まだあまり知られていないが、郡司氏は現在40代の料理人の中で最も注目すべきひとりだ。
漫画『美味しんぼ』がきっかけで料理に興味を持った彼は、大学在学中に親の反対を押し切って料理の道を志し、専門学校へ。卒業後は憧れの名店「京味」で修業するため、半年ほど悩みながら策を講じた。
「当時『京味』は弟子を募集していなかったんです。でも私は諦められず、大将に直談判するために客として店を訪れました。そうしたら『君、料理やってるの? じゃあウチに来なさい』と言ってくださって、17年間修業させていただいたんです」
郡司氏は「京味」の大将が「味」の一字を授けた最初の愛弟子とあって、看板の字は大将が自ら揮毫したそうだ。
7席のカウンターで出されるおまかせコースは2万7000円(税別/松茸と蟹の時期は3万5000円)。コースに登場する11品は、旬の食材の素顔を生かした、飾らぬ美味しさの料理ばかりだ。
冬と春の食材が同居する3月の献立の1品目は、根菜がたっぷり入った粕汁。外気で冷えた体を温める熱い粕汁は、素朴ではんなりとした関西の味だ。
「余計なことはしない」
続いて登場するのは唐墨やササガレイ、わらびの胡麻和えなど、派手さはないが選り抜きの食材を生かした前菜の盛り合わせ。揚げて出汁で炊いた蕗の薹は口の中でなめらかに崩れ、ほろ苦さと出汁の優しい旨味が心地よく広がる。
3品目は琵琶湖に春の訪れを告げる氷魚、すなわち鮎の稚魚が主役。あっさりとした柔らかな氷魚は、木の芽が香る冷たい大根おろしと洒落た相性だ。
三寒四温の陽気にふさわしく、次は冬の名残の「牡蠣の土手鍋」。小さな土鍋でぐつぐつと煮える鍋の地は赤味噌と白味噌のバランスが絶妙で、濃厚な牡蠣の旨味と調和し、至福の境地へ穏やかに誘う。変わった料理はひとつもないが、季節や気候に合った料理を食べることの喜びがある。
「『余計なことをしない』という大将の教えを守っているだけです。独立したての頃は『京味』と同じ料理を出しちゃいけないと思って独自の料理を出したりもしましたが、店に来てくれた大将から『変わったことをしなくていい』と言われ、納得してやめました。大将の言うことに間違いはないんです」
“余計なことをしない”料理は、良い素材があって初めて成り立つもの。食材は郡司氏が自分で見つけて仕入れることもあるが、大半は師匠と同じ業者から仕入れているという。
そのため、コースの中には「京味」譲りの珍しい食材が登場することもしばしば。たとえば「芽芋」はズイキ(里芋の葉柄)と似ているが、里芋から伸びた芽を軟白栽培させたもの。実は栽培に手間のかかる高級食材だ。「岩茸」は崖地で穫れる希少な高級食材で、名前はキノコを連想させるが苔の仲間。この芽芋と岩茸を合わせたおひたしは一見田舎料理のように素朴だが、正体はすっきりと洗練された京(みやこ)の料理だ。ずっと食べ続けていたいような魅力に引き込まれながら食べ終えた時には、この淡い味こそ日本料理の真髄ではないかと思わせられる。
走りの筍に甘鯛を挟んで揚げた6品目の「筍の挟み揚げ」は、細やかな仕事が美しい一品。筍も甘鯛もそのままで美味しい食材だが、
「筍と甘鯛は、相乗効果が生まれる組み合わせ。合わせることでそれぞれの甘みと旨味がふくらむのです」
と郡司氏。凝った料理には、それなりの理由がある。
7、8品目は、日本料理の花形であるお造りとお椀。お造りは鯛の皮目に熱湯をかけてから冷やした“松皮造り”とメジマグロ、お椀は海老しんじょうだ。お造りの清らかな旨味は日本酒を呼び、凛とした香り高いお椀には背筋が伸びる。お造りもお椀も、“余計なことをしない”凄みが舌に染み入るようだ。
「魯山人ごはん」
3月のコースの後半は、「若狭の甘鯛の塩焼き」「湯葉と筍と揚げわらびの煮物」に続き、食事となる。食事は「筍ごはん」のような季節の炊き込みごはんとなる場合もあるが、初来店の客に出されるのは定番の「魯山人ごはん」。炊きたてのごはんに細切りの利尻昆布と鰹出汁をかけたこの料理は北大路魯山人が考案したと伝わるもので、最初に再現したのは「京味」の大将だ。郡司氏の「魯山人ごはん」は、そのレシピを継承したもの。お茶漬けのようにかき込めば、さらりとしたごはんの甘みと昆布の気品、鰹出汁のふくよかな香りが相まって、ぱっちりと目が覚める。9割がお代わりするというのも納得の鮮烈な美味しさだ。
一体どうしたらごはんと昆布と出汁からこの美味が生まれるのか?と尋ねれば、
「昆布は提供する10分前からすり鉢に入れて鰹出汁とかき混ぜます。そうすると昆布の粘りが出るんです」
と教えてくれる。料理が楽しくてたまらないという様子で語る郡司氏は、「京味」の門を叩いた青年時代を偲ばせる、真っ直ぐな人柄。故に〆の甘味「本わらび餅」のきな粉まで、手をかけて本物を味わわせてくれる。
「日本流の本流を受け継いでほしい」という師の願いを託された「味ひろ」は、3カ月先まで予約を受付中。6月は鮎と鱧目当てのリピーターが増える季節ゆえ、予約は是非お早めに。
©MEGUMI KOMATSU





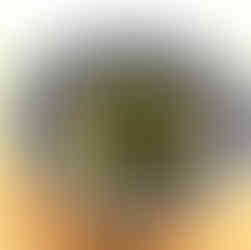






コメント