銀座あさみ(銀座)
- 小松めぐみ
- 2018年4月27日
- 読了時間: 3分
更新日:2018年8月23日
東京都中央区銀座8-16-6 ときわぎ館1F ☎︎03-5565-1606
営業時間11:30~14:00LO、17:00〜21:30LO 定休日:日曜、祝日
予算:コース¥15,000〜(税別) http://www.ginza-asami.co.jp
*2015年「週刊新潮」46号掲載

京都の郷土料理たる
京料理の洗練の味わい
京料理は京都の食材と風土ありきの料理ゆえ、京都で味わうのが一番。しかし、東京で味わうなら、王道の京料理を得意とする「銀座あさみ」がいい。
ご主人の浅見健二氏(56)は、東京出身だが、修業を積んだのは都内の京料理店。そのため、2000年に開業してからも京料理を作り続けている御仁なのだ。
「私の料理は、料亭の料理ではなく、華美な飾りをしない割烹の料理です。京料理は、元は京都の郷土料理ですので、食材は西のものを仕入れています」
その特徴は、コースの始まりから顕著だ。1品目は濃厚な蟹味噌の風味をたたえながらもさっぱりとした「蟹味噌の豆腐よせ」で、洗練された味わいはいかにも京料理の趣。
2品目の「香箱蟹」は、いわゆるズワイ蟹の雌で、京都では「コッペ蟹」と呼ばれて愛される、晩秋〜冬の味覚だ。手の平ほどの甲羅に盛られた脚の身は、ズワイ蟹よりも濃厚な味わいで、土佐酢をつけると甘味が引き立つ。脚の身の下には、ほぐした抱き身と共に「外子」「内子」と呼ばれる2種類の卵が詰められているのだが、受精卵である「外子」は、プチプチした食感が独特。朱色の塊状の「内子」は受精前の卵で、コクと旨みが凝縮されているどちらも香箱蟹ならではの魅力だ。
食欲が満たされると、赤い甲羅が映える黒い皿の美しさにも、改めて気が付く。聞けば、器は楽焼だとか。楽焼といえば、黒楽茶碗で知られる茶の湯の陶器。浅見氏も32歳の時に茶道を習い始めたという。
「茶道の本場である京都の料理は、茶の湯と切っても切れない関係。そもそも『懐石料理』は、茶事の際に来客をもてなす『茶懐石』から始まったものです。ウチの店の料理は宴会でお酒が進むような『会席料理』ですが、器を重視する茶懐石の心は大切にしています」
お造りには醤油とポン酢と、自家製の「煎り酒」を出すのも、この店の流儀である。
「煎り酒は酒に梅干と削り節、昆布を入れて煮詰め、薄口醤油で味を調えたもの。醤油より古い調味料で、京都では今もよく使います」
濃口醤油に慣れた口には薄味だが、白身魚には抜群の相性。煎り酒のほのかな酸味と塩気で、白身魚の繊細な旨味が引き立つのだ。
続いてお椀は、ウズラのつみれが主役の「ウズラ丸」。香り高い吸地は、出汁の昆布の旨味が生きて、ウズラの旨味にも負けないほどだ。
「京料理の出汁は、昆布が主体。昆布の色で湯が琥珀色になるくらいまで1〜2時間煮出しています」
7品目の焼物を挟み、8品目は「海老芋と湯葉の炊き合わせ」。海老芋は今が旬の京野菜で、そのねっとりした食感には、湯葉を合わせるのがお決まりだ。
締めの定番の鯛茶漬けは、濃厚な胡麻ダレを絡めた明石の鯛の刺身が、茶人好みの黒織部の器に盛られて登場した。まずはご飯にのせて鯛と胡麻の濃厚な旨味を堪能したら、後半はお茶をかけて味わう趣向で、後味はさっぱり。
それにしても、これが郷土料理とは。千年の古都たる京都の文化度の高さに圧倒されるのだった。
©MEGUMI KOMATSU





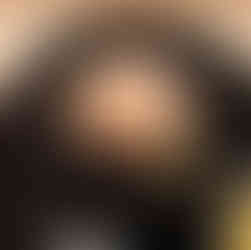






コメント